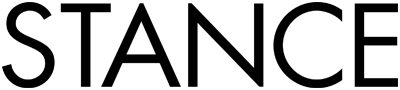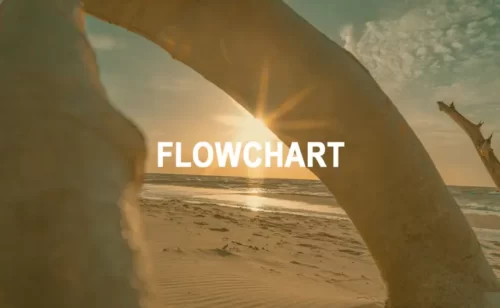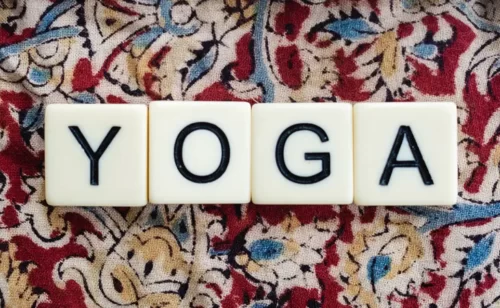さっそくカラダは何でできているのか、パッと頭に浮かぶのはなんでしょうか?
筋肉?骨?内臓?神経?
もちろんどれも正解!
カラダの動くしくみ
今回はカラダを動きについてお伝えするということで、「骨」と「筋肉」、そして動く方向や角度などに関係のある「関節」についてです。
1. 骨について
理科室にあったガイコツの模型で、だいたいのイメージはつくと思います。長いのやら短いのやら小ちゃいのやら形も大きさも様々で200以上もカラダの中にあり、硬くてカラダを支えるのが骨の役目です。カラダが柔らかいといっても骨の形が変化するわけではありません。長い時間同じ場所に負担かかりつづけることで変形することはあります。
皮膚と同じように骨にも代謝があり、骨を作る細胞と壊す細胞がバランスよく働いていて入れ替わり新しく生まれ変わっていきます。
骨粗鬆症では細かいカラダの中の仕組みは端折りますが、二つの働きの細胞のバランスが壊す細胞の方がたくさん働いていて骨がスカスカになることで起こります。
2. 筋肉について
筋肉も場所や働きによって大きさや形も様々です。
特徴は縮んだり緩んだり(元の長さになる)します。筋肉自体が長く伸びる動きはなく引っ張られて伸ばされることができます。
筋肉を包んでる膜を筋膜と呼び、カラダの動きに大きく影響していると言われています。小さい筋肉を筋膜が包んで、それをいくつかまとめて大きい筋膜で包んでそれをまたさらに筋膜で包んでカラダ中に張り巡らせているので第2の骨格と言われたりもします。
この隣り合う筋膜や脂肪、皮膚は滑走することでスムーズな動きが生まれるのですが、カラダを動かさないことで古い飴ちゃんと包み紙の様にへばりついてしまいます。
3. 関節について
骨と骨が向かい合ったところを関節と呼びます。骨と骨をつなぐように筋肉がくっついてその筋肉が縮んだり元に戻ったりすることでカラダが動くというのが大まかな仕組みです。
ですので骨と骨のつなぎ目はすべて関節です。関節も様々な形があり扉の蝶番のような動きがイメージつきやすいかと思います。
筋肉が骨と骨をつないで縮んだり緩んだりすることで関節に動きが生じて、カラダが動きます。複雑な動きをたくさんの関節が動くことで生まれます。
そのほかに筋肉の動きを制御している神経や関節をスムーズに動かすための関節周りの結合組織(靭帯や関節包)など、それぞれの働きによりチームでカラダを動かしています。
コリや痛みについて気になる方も多いと思います。一言で原因を言うことはできず様々なことが考えられますが、まずはご自身のカラダの動きを観察してみてどんな時に痛みが出るのかどんな姿勢が多くてどこに負担がかかっているのか…
ヨガレッスン中はご自身のカラダを観察するチャンスです!できるできないではなくカラダの動きに注目してみてください。
こんなに動くの?とか変に力入れてるなぁーとか気づくと変われる初めの一歩になります。